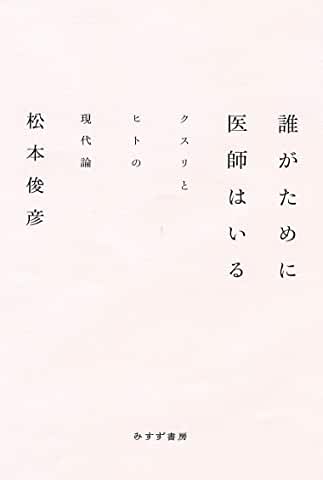54 松本俊彦 みすず書房
高野秀行がこの本を褒めていた。それを夫がどこかで見かけて、借りたら面白かったというので読んだ。面白かった。
作者はアディクション(嗜癖問題、依存症など)を専門とする精神科医である。何故アディクション臨床なんかにハマったのか、から始まって、様々なアディクションの現状、問題点などと、時に自分が何故、医者になったのかを過去の記憶とともに書いている。非常にわかりやすく、読みやすく、興味深い文章である。
覚醒剤やアルコールなどの依存症の問題は、全く他人事ではない。私も若い頃は飲むのが大好きで、うっかりするとアルコール依存症まっしぐらだったかも、とすら思う。が、いまや健康上の理由で飲酒は極めて控えめになった。覚せい剤は流石にやったことはない。が、悩みの果に軽い安定剤は飲んだことがあるし、それに頼ってしまう気分はわからなくもない。人は、なにかに依存しがちである、とつくづく思う。
覚醒剤依存は快楽を求めた結果ではなく、苦痛を避けるための方策である、という指摘は重要である。気持ちよくなっちゃうためにじゃない。苦しみを忘れたいだけなのだ。
作者は、自分の中学時代を最初に振り返って、よく話をした同級生が、如何にしてシンナーに染まっていったか、そこから脱し得なかったかを語っている。それは苦い苦い話だ。それが、彼が精神科医になる原点だったらしい。
「絶対貧困」で、何日も食べ物を口にしていないバングラディシュのストリートチルドレンが、やっと収入を得たら、それで食糧を買わずにシンナーを買って吸引、陶酔していたという話を読んで衝撃を受けたのが忘れられない。人は、食料よりも陶酔を求める。それこそが苦痛から逃れる方策だからだ。
現代のアディクション患者の新興勢力はベンゾ依存症患者であるという。精神障害の治療のための処方薬である睡眠薬や抗不安剤などの依存である。ベンゾ依存症患者は平均十二ほどの精神科を渡り歩き、それぞれから睡眠薬や抗不安剤などを処方してもらって、それを日々多量に服用するようになる。こうしたベンゾ依存法患者の台頭の一つの契機として南条あやの遺稿集「卒業式までは死にません」が挙げられているのに、私はあっと思った。私もその本を読んだことがあり、そして読後の嫌な感じを忘れられずにいたからだ。
南条あやは、伝説のブロガーでもあった。リストカットをし、いくつもの精神科医を巡り歩いて向精神薬を服用するさまを実に生き生きと語り、自殺念慮や薬剤依存との戦いを記録し、高校卒業後にオーバードーズで死に至った。彼女の周囲には、精神科医も、彼氏も、彼女の現状を知っている父親も、教師もいたが、誰も彼女を救えなかった。彼女はまるでアイドルのようにネット上で祭り上げられ、その死も美化され、多くの支持者が表れた。それがベンゾ依存法患者を増加させたという。
心の病はこころの風邪なので、気軽に受診を、と勧められる。だが、その結果として与えられる抗不安剤が時にベンゾ依存症患者への入口となる。この矛盾。だから、切れ味の良すぎる薬は処方してはいけない、と作者はいう。だが、人は楽になりたい。アディクションは、いたちごっこである、とつくづく思う。
とどのつまりは、人は幸せに生きるべきである、という当たり前の結論にたどり着くしか無いのだろう、と思う。度を越した苦痛を耐えねばならないような人生は、なんとか助けねばならない。子供は、幸せに成長せねばならない。大人も、自分を自分で支えられる程度の環境と力を持てるように配慮されねばならない。そういうことだ。そういう当たり前の、誰もがある程度の幸せを得られるような社会を目指すことでしか結局はこうした問題は克服されない。だからこそ、アディクションは続く。そんなことを、私は考えた。