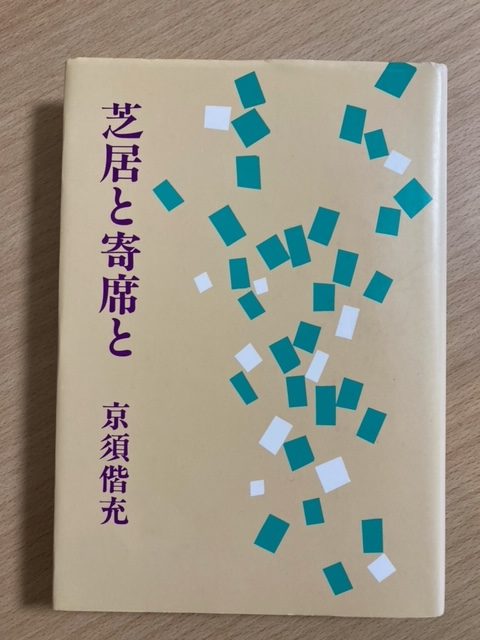141 京須 偕充 青蛙房
今はなき「伊集院光とらじおと」にこの作者がゲスト出演しているのを聞いた。六代目三遊亭圓生の「圓生百席」のレコード化のプロデューサーだった人である。そのほかにも多くの落語会をプロデュースし、録音してきた。落語だけでなく、歌舞伎や講談など古典芸能に詳しい人である。その話がとても魅力的だったので、古書店でこの本を見つけて思わず買った。買ったけれど、ずっと棚に積みっぱなしでやっと読了した。30年以上前の古い本で、奥付に手押しの「京須」の印と限定番号が貼ってあり、著者現住所、電話番号まで印刷してあるのには驚いた。
昭和17年生まれの作者が子供のころからどんな芝居や落語に触れてきたのかという話である。歌舞伎の話が多い。かつての名優のエピソードが、目の前の出来事として描かれている。見る目のある人にとっての歌舞伎とはこういうものか、このように見るものかと驚かされるところも多々あるし、落語の出来不出来も、なぜそう思うのかが丁寧に説明されていて腑に落ちる。幼いころから芸に触れてきたからこその確かな目と耳を感じさせられる。
それは、いい。それは良いのだが、一つだけどうにもやりきれないエピソードがある。歌舞伎の大向うからの掛け声の話である。見物客の三分の二近くが女性なのだから、掛け声が男ばかりだというのは不公平だ、と書きながら、女性の掛け声には違和感がある、と書いている。舞台では男が女を演じていて、見物もそれを納得しているという古くからの約束事を反故にされかねない危険を女性の声ははらんで響く、というのだ。だから、独唱の掛け声は自制してほしい、という。そして「天衣紛上野初花(くもにまごううえのはつはな)」という大舞台で四代目中村雀右衛門へ「京屋ッ」と女性の掛け声がかかったときのことをとうとうと書いている。
何度目かの女性の「京屋」の掛け声に「やめろ女」というドスのきいた声が場内にひびく。少々酩酊の男らしい。「京屋ァー」「黙れェ女ァ」の険悪なやり取りが続き、笑いだす客まで出る。明らかに観劇の邪魔になってきた時点で女性の声が止まる。そしてまた名舞台に皆が集中するのだが、盛り上がったところで一斉に大向うの「京屋ッ」が響くと、それにかぶせるように「女、どうした?」と、くだんの酩酊男がかぶせる。
国立劇場が寄席のように笑った。これがこの日最大の観劇妨害だったが、私は少しも腹が立たなかった。
(引用は「芝居と寄席と」京須 偕充より)
これを作者は粋だと感じたのだろうか。少しも腹が立たないのは、彼が男だからではないだろうか。女性が男性と同じように大向こうから掛け声をかけるだけで、ここまで侮辱され、否定され、笑いものにされる。それが粋なエピソードであるかのように書かれる。時代もあるのかもしれないが、「女のくせに、分もわきまえず」という視線が、私にはひどく腹立たしく読めた。
と思ったら、アマゾンのレビューに、同じような感想を書いている人がいて、その人(実は作家でもある)が私はあまり好きではなかったのだが、この件に関しては強く共感した。