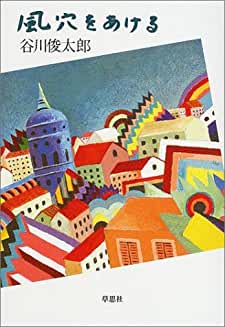「風穴をあける」 谷川俊太郎
「ひとり暮らし」(12/17 日記参照)が個人的なエッセイが主流だったのに対し、この本は、「読む・書く・人」のテーマで集められている。
「読む・書く」は」谷川氏の、言葉に対する真摯で鋭く誠実な姿勢が鮮明に感じられる。長編はかけない、と彼は言う。これほどまでにクリアで明らかな言葉を選び続けると、そぎ落とすものが多すぎて、長編など書くまでも無いのだろうか、などと浅薄な私は、ふと思ってしまう。
この中の「教室を批評すること」を読むと、これをもし読んでいたら、学校の先生方は、先日の読書会に谷川氏をお呼びすることをもっと恐れ、あるいは拒絶したいと考えたのではないかと思う。そもそも、なぜ、みんな、無邪気に「有名な詩人が来てくれる」としか捉えないのか、という疑問を私はずっと抱いていた。子どもたちのために、ぜひおいでいただきたいとは思うけれど、教師陣それを嫌がるのではないか、あるいは、もし、喜ぶとしたら、それはなんと勇気があることだろう!と、まだその企画が夢でしかない時点で、私は考えていたのだけれど。
画一的な答えを予想し、求めるところがあるという点で、現代日本の教育とマス・メディアには共通点があるから、むしろこれは自然な成り行きと言ってもいいかもしれないが、私にとっては一種衝撃的な発見だった。テレビの公開番組と小学校の教室が同じものであっていいはずはないというのが私の反応だが、おそらく教師自身はそれに気づいていない。かえってインタビュアーの技術を無意識にまねることで、教室における時間の流れを効果的にし、生徒たちから学校に対する違和感を取り除こうとしているのかもしれない。(中略)
もうひとつ、これも何度も論じられていることだが、教材にするテキストの選び方が私には納得のいかないことが多い。教科書にのっているテキストの場合は、教科書編纂委員たちの力量や考え方も問われるが、それについても無批判な教師がほとんどであるような印象を受ける。基本的には教材として完璧なテキストなどというものはあり得ないと私は思うから、教師はたとえそれに自分が深い感動を覚えたとしても、そのテキストを教材として使う場合には、批評的に読み直す必要がある。(中略)
批評を介在させない理解はないと私は思う。教師が取り上げた教材を神格化していては、生徒たちの間にも批評は育たない。だがそのためには批評に耐えるテキスト、読みを深めていくことのできる作品を教材にしなければならないだろう。
(「風穴をあける」谷川俊太郎 より引用)
また、河合隼雄氏について書かれた文章に、私は、先日の読書会における基本的な谷川氏の姿勢を思い出した。彼は、子どもたちの質問に、ほぼ必ずと言っていいほど、「わかりません」と答え、また、「なぜ君はそれを知りたいと思ったの?」と尋ね続けられたのだ。
河合さんがよく口にされる言葉が三つある。ひとつは「分かりませんなあ」、もうひとつは「難しいですなあ」、そして三つ目は「感激しました」である。(中略)
もちろん河合さんと私では、「分からないこと」の深さが違う。私が「分からない」と思ってる次元よりはるかに深い次元で河合さんは「分からない」と思っているに違いない。それでもその「分からないこと」が、簡単に答えの出るような「分からなさ」ではないということを、私たちは「分かり」あえる。安易に答えを出すよりも、まず「分からない」と思うほうが答えに近づく道だということを、私は納得する。
(「風穴をあける」谷川俊太郎 より引用)
この本の最後、「人」のテーマでは、亡くなっていった何人かの大切な友人たちのことが書かれている。武満徹、寺山修二、もちろん、河合隼雄も含めて、他にも大勢。彼らのことを繰り返し思い出すことが、新しい人たちに会うのにもまして、今の私を励ましてくれる、という谷川氏の言葉が、深く胸に響く。ピーター・グリリに「トオルとよい友達でいてくれてありがとう」と葬儀の席で言われ、自分も同じことを言いたかったのに、しどろもどろになったというエピソードが、人と人との間に流れる暖かく美しい感情をくっきりと教えてくれる。
2009/1/9