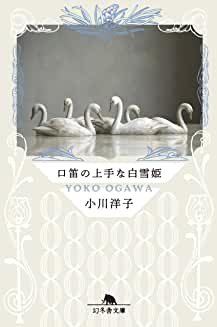29
「口笛の上手な白雪姫」小川洋子 幻冬舎
相変わらず、小川洋子の世界は不思議である。前回「ことり」で、自分独自の言語を話す兄がいたように、この本でも、自分にしか見えない人や、自分にしか理解出来ないものが登場する。それはとても不思議で、信じられないような存在なのだが、登場人物にとって、無くてはならないものなのである。
吃音に悩む少年の声を箒と塵取りで掃除し、ズレを修正する小さな「先回りローバ」、大きすぎて自分というものを把握しきれないままに死に、剥製となったシロナガスクジラのようなかわいそうな存在を書きつける「かわいそうリスト」。全部で八篇の、不思議な物語が収められている。
物語の主人公はみな、この世にどこか居づらさ、収まりの悪さを感じている。そして、その違和感を修正するためのすべをどこかに隠し持っている。それは、普通の世界から見て奇妙なものであっても、彼らにとっては大事な無くてはならないもの、自分の人生を支えるものなのだ。
この本を私は実家に向かう新幹線内で読んだ。実家には、年老いた母が一人で暮らしている。最近は、母といろいろな話をする。母は、私のことを驚くほど知らなかったのだな、と思う。
別に責めたり恨んだりしているのではない。毎日共に暮らしていても、家族であっても、分かり合えることなんてほんの少しだ。私も子どもたちの何を知っているかと問われると、いや、ほんのちょっとだけですけど、としか言いようがない。
子供の私は、思いを上手く表現できず、親の思いや願いにどこかで縛られ、けれど、それに答えきることもできず、ぼんやりといろいろなことを考えていた。親に私が質問しても、本当に知りたいことに答えてくれるとは限らなかったし、わかってもらえることばかりでもなかった。
そんな中で、私はひたすら本を読み、夢想し、考えを繰り広げていた。なぜ、どうして。こうだったら、ああしたら。ぼんやりとする私の頭と心の中にはあらゆるものごとが広がり、溢れ、だだ漏れていた。
小川洋子の小説を読むと、そんな感覚を思い出す。不思議に満ち溢れ、脈絡も整合性もなく、ただ、訳もわからないけれど私を支えてくれた世界。そういうものが、だれの中にでもあるのだと思えるような。
小川洋子の小説は、だから、わけがわからないのに懐かしく、心地よいのだろう。
2018/6/14