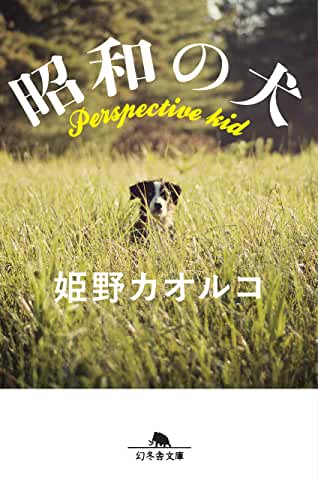168
「昭和の犬」姫野カオルコ 幻冬舎
直木賞受賞作。直木賞とか芥川賞と聞くと、むしろ読む気が失せてしまう悪癖があるために、未読だった。もっと早く読みゃあ良かったなあ、と悔やまれる。「近所の犬」を先に読んだおかげでこの本を知って、ラッキーだったと思う。
人生の様々な局面で、犬が心の支えになった、というお話。結構なつらい日々が低温で淡々と描かれている。子供に無関心な母親、いつ壊れ、激昂して痛めつけに来るかわからない父親。嬰児の頃から他人に預けられ、親に理不尽に扱われながら育った日々。でも、それが当たり前だと思っていたから、悲壮感すらなかった。それこそが日常だった。この感覚が、ものすごくよく分かる。
私が小6の時、決してそんな仲良しの親子ではなかったのに、何故か父とチェスを打つ機会があった。負けそうな最終局面で父がずるをしてごまかした。なので、私がそれを糾弾したら、父は顔を赤くして、黙って私の手の甲に、その時吸っていたタバコの火のついたほうを押し付けた。熱かった。私は立ち上がって、そのまま家の外に飛び出した。札幌の冬の日で、上着無しで外に出るのは危険なことだったと思う。父は、追いかけてきて私を捕まえ、無言でメンソレータムを私の手の甲に塗りたくった。その時、私が父に何を言ったのか、なにか言ったのかどうかさえ覚えてない。ただ、この人、追いかけては来るのか、と妙に冷静な頭で考えたことだけは覚えている。
その場面を思い出す時、私の心は低温のままである。なので、この小説で、父や母の理不尽な行いが冷静に淡々と描かれることに、ひどく納得するのである。そんな家庭で育ったので、それが当たり前だったので、それをひどいと思ったり、腹を立てたりする熱情が起きないのだ。ただ、「なぜ?」という疑問だけが、心の内側に溜まっていく。その感覚が、怖いほどよくわかってしまった。他にも様々なエピソードには事欠かないのだが、タバコの一件だけは明白に覚えている。とても熱く痛かったからなのかもしれないけれど、それよりも、父が明らかに間違っている、ということが子供心にもわかりすぎて、正当性のかけらもないことに気づいたからだったのではないか、と今になって思う。
「昭和の犬」の主人公のイクの父はシベリア抑留で凄惨な目にあって帰国した人だ。夜中、うなされ、嗚咽し、悪夢に苦しんでいたという。私の父も予科練で凄惨な場面に出会い、たくさんの死体を運び、死にそうな目にあってきた。そういう体験が心のなかに闇を生み出し、それが家族や子供に向かうときに染み出してきたのだろうか、とふと思う。そのことで、彼らを許そうとは思わない。というか、許すも許さないもない、と思う。そういう家庭だった、ということを何度も何度も反芻する以外に、どうしようもないではないか。彼らは死んでしまったし、私達は起きてしまったことを消し去ることもできず、その上で生きていくしか無いのだし。
イクは自分の家を脱出することだけを目標に子供時代を生き、大学で無事に脱出はできたけれど、結局、老いや病を抱えた親族の世話のために故郷と東京を行ったり来たりする生活を長く続けることになった。その積み重ねの中で、自分も体調を崩した。歩いていて、いきなり涙が汗のように噴出して止まらなくなる。苦しくなる。そんなとき、道行く犬が、近所の犬が、どれだけ彼女を助けてくれたか、癒やしてくれたか。そんなことが淡々と描かれている。同じように問題を抱えた大家さんとの正直な会話や、その家に飼われている犬のエピソードが不思議なほど暖かく胸にしみる。
イクの父は、なぜか犬を操るのが上手であった。誰もが手を付けられない荒くれるドーベルマンを素手でおとなしくさせた。そういうエピソードがところどころ登場する。父にとっての犬。イクにとっての犬。疑問には思っても、憎みきれない親。低温の語り口。そうしたものが、あまりに胸に迫って、どう感想を書いたらいいかわからない気がした。
2021/2/22