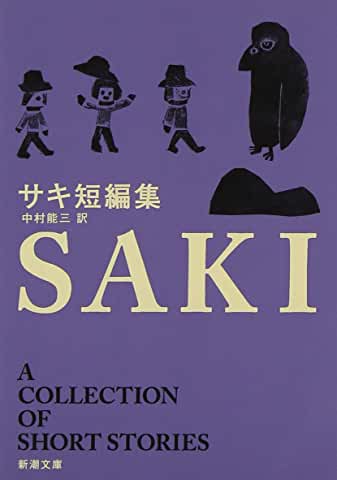158
「サキ短編集」サキ 新潮文庫
津村記久子の「サキの忘れ物」に触発されて、読んだ。茶色く変色したページに、小さい古めかしい活字。いかにも翻訳しましたという文。私が生まれる前に出版された本だった。
「泊り客の枕元に、O・ヘンリイ、あるいはサキ、あるいはその両方を置いていなければ、女主人として完璧とはいえない」とE・V・ルーカスは言ったそうだ。誰だか知らないけどさ。確かに、洒落た短編である。O・ヘンリイよりかなり皮肉屋で、乾いたユーモアがある。
「サキの忘れ物」に登場した、牛専門の画家の話は、なるほど、面白かった。高校を中退して、自分の人生に何の意味もないと思っていた女の子が、アルバイト先に客が忘れていったサキの本を読んで、本を読むって面白いものだな、と思った、という流れがとてもよくわかる気がした。そこにはこんなふうに書いてある。
その話を読んでいて、千春は、声を出して笑ったわけでも、つまらないと本を投げ出したわけでもなかった。ただ、様子を想像していたいと思い、続けて読んでいたいと思った。本は、千春が予想していたようなおもしろさやつまらなさを感じさせるものではない、ということを千春は発見した。 (引用は「サキの忘れ物」津村記久子 より)
その子は、今まで一度も本を最後まで読み通したことがなかった。高校は楽しくなかったし、友達は、彼女をバカにし、ものやお金をせびるだけだったし、恋人は浮気相手として彼女を扱った。親は彼女に興味がなかったし、誰かにまともに取り合ってもらったことなんて一度もなかった。そんな彼女が、サキを読んで、ちょっと面白いな、と思い、本を読むことを覚えた。本は、何かを教え込もうとするのではなく、自分で物を考えたり、想像したりする助けになるだけのもので、それが彼女を変えてくれた。そして、彼女は、それがきっかけかどうかはわからないけれど、アルバイト先を変えて、ちょっと離れた本屋で働くようになったのだ。
ただそれだけの話なのだけれど、私は胸が詰まるような気持ちになった。本ってそういうものなのだ、と思う。思えば、私も高校生くらいまで、自分が何の価値もない人間のように見えて、誰もまともに取り合ってくれる存在なんかではないと思いこんでいた。(今思い返すと、それでも私のことを大事に思ってくれる人は、実はそれなりにいたのだけれど、当時はそれがわからなかったのだと思う。)ただ、私には本があったから。
本を読んでいる限りにおいて、私は自由だったし、何でもできたし、私の存在には意味があった。それが私を助けてくれていたのだと思う。そういうことを、私は「サキの忘れ物」と「サキ短編集」を読みながら、思い出していた。「サキの忘れ物」の千春が愛おしいと思った。そして、自分には何の価値もない、誰にも大事にされていないと感じている世の中のたくさんの子達が、どうか、どうにか、そうではないことに気づけますように、そのことに気づけるような本と出会えますように、と祈りたいような気持ちになった。
サキは、ちょっとした出来事を、乾いたユーモアと皮肉を込めてさらっと描く名手である。P・G・ウッドハウス「ジーヴスの事件簿」のような面白みがあった。もっと大事にされて良い作家だと思うけどなあ。
2021/2/2