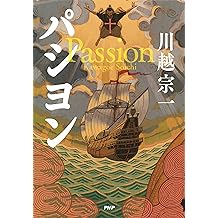179川越宗一 PHP
2021年から2023にかけて河北新報、静岡新聞、南日本新聞、長崎新聞、琉球新報などに連載された作品に加筆修正した時代小説。長編である。関ケ原の戦いから江戸初期にかけてのキリシタン受難の物語だが、弾圧される側だけでなく、弾圧する側の視点もともに描いている。
私の育った家はクリスチャンホームであった。父がミッション系の大学を出ており、両親ともにごく穏当なプロテスタント信者で、幼いころから日曜日は教会に通った。小学生のころから歴史が好きだった私は島原の乱や江戸時代のキリスト教弾圧に興味があり、それをテーマにした児童文学も何冊か読んでいた。正しいと信じるもののために殺されていく話が多く、どうしてこんなひどい目にあわされねばならないのかと思っていた。弾圧される側はあくまでも被害者であり、正しい立場の者として描かれていた。だが、この物語は、弾圧される側のキリスト教信者が地元の寺社仏閣を打ち壊したり、異教徒は人間ではないから殺してもいいと言いあう姿も描いている。一方では、弾圧する側の人間の葛藤や苦しみ、平和を希求する姿も描いている。であるからこそ、リアリティがある。人間は一方的に正しいだけのものと、間違い続けるものの二手に分かれることはない。どんな人にも正しさはあり、闇もある。ましてや信仰というものは、もともとは人の心を平穏に導くためのものでありながら、それが争いの元ともなる。その矛盾は一筋縄ではいかないはずだ。
キリスト教を信じる者、それを抑圧する者、それぞれの人間模様は、実は今、ガザで起きていることや、アフガニスタンで起きていること、そして世界各地で起きていることと同じだと思う。正しいと信じるものが違っているだけで、人は憎みあったり殺し合ったりしてしまう。でも、その一方で、宗教の違いを超えて共生し合い、助け合いたいと願う人間もいる。この物語でも、はりつけにされるキリスト教徒の成仏を祈る浄土宗の僧侶の姿も描かれている。そういう人間もいる。いろいろな人間がいるのがこの世というものだ。
私は結果的にクリスチャンになることはなかった。子ども時代、島原の乱の物語を読んでも、本当にキリスト教だけが常に正しかったのか、よくわからなかった。戦わなければ死なずに済んだ農民だってたくさんいただろうし、転べば(宗教を手放せば)許されるのなら、表面上転んだと口にして何が悪いとも思った。それをせずに、ひどい目にあわされて死ぬのが美しいことだとも思えなかった。その頃に単純に抱いた感情が、この本を読んでいてたくさん蘇ってきた。何が正しいのか。何が正解なのか。この歳になっても私はしかと体得してはいない。けれど、これだけが真実であると決めつけることへの迷いのようなものは、誰もが持ち続けていいものだし、持ち続けることでわかることもある。人は自由で、いろいろな考えをもっていい。ただ、自分と違うものを侵してはいけないのだ。
それにしても、あのころ、日本を脱出してマカオ、ゴアを経てヨーロッパにまでたどり着き、大学で学んで司祭の資格を取った日本人が何人もいるとは思わなかった。もしかしたらそういったエピソードも子ども時代に読んだのかもしれない。が、当時はまだその時代にヨーロッパに渡ること、大学で学ぶこと、それから日本に戻ることがどんなに困難なことか、具体的にはわからなかったのだと思う。これは史実か?と疑って検索したら、実在の人物ばかりであった。主人公のマンショ小西は対馬藩主とキリシタン大名小西行長の息子で、岐部ペイトロ渇水やミゲル・ミノエスらとともに、本当にリスボンで司祭になった人であった。それがどんなに大変ですごいことか、今の私にはようやくわかる。日本に帰国した彼らは、ことごとく捕まり、転ぶことなく最後には殺された。だが、ひどい殺し方をした側にも、様々な人間模様があり、人生があった。誰もが幸せを願いながら、踏みにじり、殺すことになっていく。拷問を受けながら、「お前を許そう」と弾圧者にいうマンショ小西の言葉が、深く心にしみた。人は、きっとどこかで許し合わないといけない。
日本における当時のキリスト教の史実はわかっていて読んだのだから、結末は当然思った通りであった。が、それは今もなお続いている問題である、という視点が私には新鮮であった。
なかなか本が読めなかった。実家にしばらく行っていた。ついに90歳になる母が一人で暮らしている。身の回りのことはすべて一人で出来はするのだが、衰えていることは間違いないし、何より寂しさがいけない。毎月泊りがけで手伝いに行き、近居の姉が毎週様子を見に行っているが、老いて一人で暮らすとはなかなか大変なことだ。いつもと少しでも違ったこと、新しいことが起きると対処が困難となり、助けが必要となる。それを支えるのが私の仕事なのだろうと思ってはいる。老いるとはどういうことなのかを学ばせてもらっている、と考えればいいのだろうな。
ところで、この本の作者を私は知らなかった。こんな長編を新聞連載して、最後まで行き着くのかと編集者は心配にならなかったのかしら、半分くらいまで書いてから連載は始まったのかしら、頓挫しないようにどんな工夫があったのかしら、などとまるで新人作家を担当する編集者の気分で読んでいたら、あらら、この人、直木賞作家で、この作品でも中央公論文藝賞を受賞しているのね。賞に興味がないとこういうことになるのだなあ。反省。