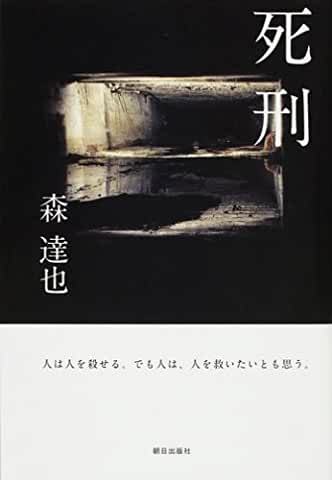「死刑 人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う。」森達也
死刑制度については、もう、議論はとりあえず出尽くしているように思えてならない。存置派も、廃止派も、それぞれの論理を持っている。そして、それは永遠にかみ合わない。だから、この本を読んで、何か新しい視点が持てるとは思えなかった。そして、それはその通りだった。その通りだったけれど。
森達也は、情緒的すぎる、と思う。自制的で感情を殺して淡々と書き進めながら、一番重要なことを読者にじわじわとしみこませる沢木耕太郎のようなやり方と、対極をなすように感じる。ましてや、死刑などというものを論じるのに、感情はむしろ邪魔になるのではないか、と思ったりもしていた。
けれど。
結局のところ、人の生死にかかわる事柄を、情緒を抜きに話すことは出来ないのだ、と読み終えて思う。と言うより、人は感情の生き物であり、感情を抜きにしては何も語ることはできない。語り方の方法はいろいろあるけれど、森達也のやり方が、死刑を論じる時に無意味だとは思えない。どっぷり自分の感情と向き合うところから出発した方が、実はいろんなことが見えてくるのかもしれない。
存置派と廃止派の論理をここで改めて紹介しようとは思わない。ただ、「あなたが愛する人を殺されたとしたら」という仮定の質問に対し、私は第三者であるから、第三者としての立場でものを考えたい、それは重要なことである、と答えたい。犯人を自分の手で殺したい、と考える被害者遺族がいたとしても、実際にできるものではない、という証言は心に残る。法廷で、密かにナイフを握り締めて傍聴する遺族はいる。どんなに警備官がいても、本気で殺そうと思えばできないはずはない。覚悟を決めて、やってやると思って法廷に行った遺族はいるけれど、でも、できない。警備のせいではない。敵討ちと言うのは、それほどに恐ろしく、難しく、実行不可能なものなのだ。だから国家が制度としてそれをやるのだ、という証言。でも。それほどに実現困難な、恐ろしいことを、国がシステムとして肩代わりすることが、被害者遺族の「癒し」になるのか、という疑問はいつまでも終わらない。
光市の事件の報道に、ずっと違和感を感じていた。弁護士叩きに、不快感を感じていた。古くは、文京区の音羽の事件も、神戸の事件も、畠山鈴香の事件でも。センセーショナルに、悪を報じて、殺せと言わんばかりの報道に疑問を感じていた。皆、不安を感じ、恐怖を感じ、それを、誰かに負わせて、叩きのめすことで、安心しようとしていると思わずにはいられなかった。
死刑制度の問題は、それを考えるところから始まる。人は、何を望んでいるのか。悪は、悪でしかなく、叩き潰せばいいのか。私達は、この社会でどう生きていくのか。
死刑を論じることと、自殺を論じることは、地続きだ。読んでいて、それがよくわかった。考えても、考えても、正解には行き着かないかもしれないけれど。でも、私は、死刑存置派ではない。そのことだけは、よくわかった。
2008/2/24