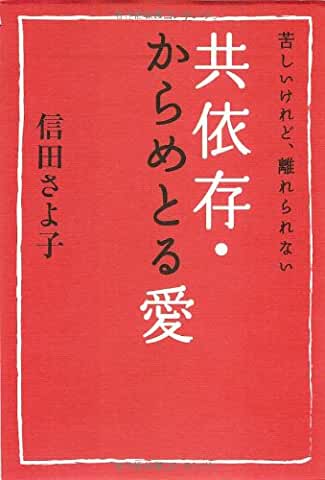87
「苦しいけれど、離れられない 共依存・からめとる愛」
信田さよ子 朝日新聞出版
母娘の共依存関係や毒親に関わる本について書くと反響が大きい。アクセス数も急激に増える。つまり、それだけこの問題は身近なものであり、かつ、出口がないということなのかもしれない。
信田さよ子をあまり読んでこなかったのに、突然何冊か読んでみたのは、自分の周囲にあまりにも当たり前のように、こじれた夫婦関係や親子関係があり、そこから脱することも出来ない人間が多いことに気づいたからだ。読めば、なるほどと思うことも多々あり、そうなのか?と疑問に思うことも多々ある。こういった問題に正解はないし、真の意味における解決というものもないから、当然のことではあるのだが。
共依存という言葉は、私にとっては、アルコール依存症の問題とともに認知されたものである。酒をやめられない夫と、その夫を、自分がいなければこの人は生きていけない、と世話をし続ける妻の関係性。夫が酒をやめることを望みながら、どこかでこの人がお酒を飲んでだめになっていく中で、私だけが見放さないでいる、ということに陶酔したり、そこに自己の存在価値を見出したりしてしまう妻。断酒しようとする夫の努力を無意識のうちに無駄にさせたり、酒の上の失敗を悔いて謝る夫を何度でも許すことで問題解決を先延ばしする。そういう意味では、共依存者は被害者でありながら、加害者であるという認識が私にはあった。
だが、この本では、それを否定する。
「ケアを行使する側が受け手よりはるかに力を持っている場合、もしくは力をもっていることを誇示したい時に共依存が発生する」、このように定義を明確化するに伴って、原点であるアルコール依存症の夫をっ持つ妻の「共依存」は多くの疑問符とともに用いなければならないことがわかる。彼女たちの夫に対する支配の選択肢の乏しさは明らかである。それはたったひとつだけ許された(ジェンダー規範にもとづいた)支配なのであり、どこかそれは傷つけられたものの復讐にも似ている。すると共依存という言葉の発生は、明らかに女性(妻)への嫌悪、蔑視を背景にしていたのではないかと推測されるのだ。妻が長年の夫のアルコール問題に疲弊しきった後に、自分がはるかに夫より力をもっていると誇示したいと欲することを私は責める気にはなれない。妻の共依存でアルコール依存症の夫が死に至る例もなくはないだろうが、その逆のほうがもっと恐ろしい。
DVについてもこの本は指摘している。DV相談窓口で対応する相談員は、ひたすら家を出て逃げることを勧め、相談者は家を出たくないので暴力を止める方法を知りたいという。この食い違いは結果として不幸な結末を招く。女性は暴力を振るわれ続け、子どもたちはその現場に放置される。相談員は「あの人は共依存である」と判断する。だがDVは殴る夫にこそ問題がある。
逃げられない妻を共依存と呼ぶことは、彼女にも責任があると認めることになるからだ。DV加害者のプログラムにおいて最も重要なポイントは、彼らの暴力は彼ら自身に責任があることを学ぶことである。なぜなら、彼らは妻のせいで暴力をふるった、妻が冷たくなければ暴力なんかふるわない、妻の責任であると考えているからだ。いってみれば、彼らは被害者意識に満ちているのであり、逆に妻は自分のせいで夫を殴らせてしまったという罪悪感を根深くもっている。これを加害者意識と呼べば、DVの加害者と被害者の意識は逆転しているのだ。そして世間の支配的な常識はこの逆転を支持していることはいうまでもない。
従ってDV被害者を共依存と呼ぶことは、逆転した加害・被害の意識を強化することになる。被害者こそ問題なのだ、という彼女たちに対する冷酷で批判的なまなざしを追認することになるのだ。だから、DV被害者に対して共依存という言葉を用いることは厳につつしまなければならない。それはDVにおける微妙な力関係を、一気に加害者よりに変換してしまう言葉として機能するからである。
身近にいるDV被害者に対して、たしかに私自身も、彼女に問題がある、と思わずにはいられない状況があった。であるにしても、やはり彼女を加害者であると言ってはならない、とつくづく考えた。暴力にさらされたものは、どこまでも被害者であり、第一に批判されるべきはやはり暴力を振るうものである。そこを抑えずして、問題は解決しない。(だとしても、では、どうしたらいいのだろうか!逃げることもせず、ただ殴られ続ける彼女に、一体何が出来るのだろうか!)
作者自身も熱中したという「冬のソナタ」をパターナリズム(父親的温情主義、父権的感傷主義)をキーワードに分析した章は、非常に興味深かった。このドラマは、主人公の女性ユジンを取り合う二人の男性の物語なのだが、二人が争うのは「どちらがユジンを幸せにできるのか」である。
この競争が成立するには、ユジンを守り、幸せにするのはユジン自身ではなく他者であること、何が幸せかの判断力がユジンには欠けていることが条件となる。つまり主体的に「私はミニョンに守って欲しい」「私が幸せになるにはサンヒョクが必要だ」などと決めることができない女性でなければならないのだ。
筆者はパターナリズムの特徴を次のように説明する。
1 自己と対象の意思を同一視するところから成立する。
2 その行為は善意・良識に従ったものである。
ここで私は昨年亡くなった父を思い出す。中学生の頃だろうか、親と子供の意見が食い違った時に、どうやって選択をなすべきか・・・といったことについて友人と話したことがある。友人はこういったのだ。「でもさ、親の願いは結局子どもが幸せになることだからさ、親に逆らったとしても、それで子どもが幸せになるとしたら、親も納得するんじゃないかな。」と。私はそれを聞いて、友人と自分との決定的な差を知った。つまり、私の親(とりわけ父)にとって、子供の幸せとは、父が決めるものであり、子自身が決めるものではなかったからだ。たとえ子ども自身が「これが私の幸せ」と主張したところで、父が「いやそれはお前の幸せではない」と言ってしまえば、子の希望などあっという間になかったものにされる。まちがいなく、そうされる。と、まだ十代中頃の私ははっきりわかったのだ。実際には、私は父の言いなりになるような従順な子供ではなかったので、その後の紆余曲折は大変なものがあったのだが。
なるほど、そういったパターナリズムの観点から見ると、「冬ソナ」は見事に説明される。そして、このドラマを見たときの、私の感じたなんともいえない居心地の悪さ、腑に落ちなさの理由が見つかるのである。
一冊読み終えて、何を感じたかと言えば、「難儀よのう・・」の一言である。共依存という関係性は、それが共依存である、と気づくことでしか脱出し得ない。だが、気づいたところでどうしようもない部分も、本当に大きい。そこから脱するのは、結局は個人の勇気であり、思い切りであり、決断でしかない。また、誰かに依存することは、非常に甘美なものでもあり、それをすべて捨て去るのは寂しいことでもあるから、程よく自立しながら生きていくことを目指すしかないのだなあ、とも思ったのであった。
(引用はすべて「共依存・からめとる愛」信田さよ子 より)
2019/8/30