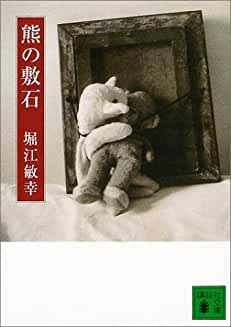117
「熊の敷石」堀江敏幸 講談社
「あとは切手を、一枚貼るだけ」の堀江敏幸である。あの作品から、友人にこれを勧められたので読んでみた。芥川賞受賞作だって。全然知らなかったのは、芥川賞とか直木賞に、ほとんど興味がないからなんだろうなあ。
どんな話か説明不能、と友人が言っていたが、たしかに。ただ、私はこの本を読んで「さまよえるユダヤ人」という言葉の意味とイメージが鮮明になった気がする。
主人公はフランス語を仕事にしていて、フランスの田舎町にいるユダヤ人の友人と久しぶりに数日を過ごす。ユダヤ人の名はヤン。そういえば、ユダヤ人が主人公の児童文学にヤンって少年が出てきたな、と思い出す。「あらしのまえ」「あらしのあと」だったかな。
ヤンとの何気ない会話。家族の愚痴である。私たちだってよく友人同士でそんな話をする。そこで語られるのは、収容所を知っている世代とそうでない世代の断絶である。おばあちゃんも、両親もイディッシュ語を話したが、ヤンは習わなかった。出身地の異なるユダヤ人が共通の言葉で語り得た時代は僕の前の世代で終わった、とヤンはいう。
そうか、イディッシュ語とは、そういうものだったのか、と私は初めて知る。国を失い、世界中をばらばらに生きるユダヤ人が、イディッシュ語という共通の言語で繋がり合う。生きる場所も環境も、もしかしたら慣習も全然違ってしまった人たちが、言葉をよすがに同じ民族だと確かめあう。ユダヤ人というカテゴリーはその様に維持されたのか。だとしたら、それはどうしてそこで途絶えたのか。小さな島国に住み続ける私たちには計り知れない歴史の積み重ねを突然感じて、私は気が遠くなるような気持ちになる。
公の悲しみなんてありうるのだろうか、とヤンの言葉を耳に入れながら私は思っていた。悲しみなんて、ひとりひとりが耐えるほかないものではないのか。本当の意味での公の怒りがないのとおなじで。怒りや悲しみを不特定多数の同胞と分かちあうなんてある意味で美しい幻想にすぎない。痛みはまず個にとどまってこそ具体化するものなのだ。ヤンが身内から話を広げていくのは、どんなに「ありふれた」事例であってもまちがいのないやり方なのだろう。大切なのは個のレベルで悲しみをきちんと伝えていくことなのだ。
(引用は「熊の敷石」堀江敏幸 より)
「熊の敷石」とは「要らぬおせっかい」という意味のフランス語表現である。熊が要らぬおせっかいで仲良しの農夫を石で打ち殺したラ・フォンティーヌの寓話に由来する「無知な友人ほど危険なものはない。賢い敵のほうがずっとましである。」という訓話である。
主人公は、ヤンとなんでもない会話を交わすことで、話す必要のない傷をあれこれさらけ出させたことを思う。それは、素知らぬ顔の冷淡な他人よりも危険な存在だったのではないかとふと思うのである。・・なんてことを考えているうちに、彼はとんでもない歯痛に襲われて、それどころじゃないよー、というところで物語は終わる。
つまるところ、この物語も個にとどまって、その感情を丁寧に追った、それだけのものなのかもしれない、と思う。そして、個を具体的にきちんと伝えることの力を、私は結構信じているのだな、と思ったりする。歯は、早く治したほうがいいね。
2019/11/1