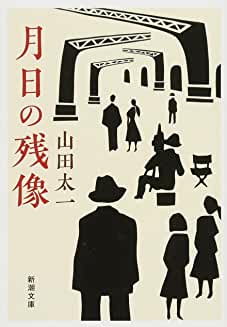180
「月日の残像」山田太一 新潮社
言うまでもなく、「ふぞろいの林檎たち」の脚本家である山田太一である。と書いて、あー、最近の若い子たち、「ふぞろいの林檎たち」なんて言ってもわかんないんだろうなー、と思う。手でりんごを放り投げるオープニング、後ろに流れる「いとしのエリー」。思い出しただけで懐かしいのに。
松竹の助監督をしていた彼が、テレビドラマの脚本家となったころ、先輩の脚本家から、シナリオというのは映画の脚本のことで、あなたはテレビドラマを書いてるんだからスクリプト・ライターというべきだ、と強く言われたという。映画人からテレビが蔑まれていたわけだ。彼はその気持がわかる気がする、と書いている。腹を立てなかったという。映画人の矜持を理解しながら、それでも彼は新たなテレビの世界で脚本家を続け、素晴らしい作品をたくさん作り上げた。
「キネマの神さま」で絶賛されていた「ニュー・シネマ・パラダイス」を最近見た。これが、素晴らしく良い映画だった。こっちは、娯楽の主流が映画からテレビに移行して、映画が廃れていく中で、もう一度映画を見直そう、という監督の強い思いが表れていた。
一人で、あるいは気心知れた家族と小さめの画面で見るテレビ。見知らぬ人、誰とはわからぬ大勢の人と共に見る大画面の映画。それぞれにそれぞれの役割があるのだと思う。
先日、昔話絵本を小学校で読み聞かせたのだが、予想以上の盛り上がりにむしろ戸惑ってしまうほどだった。昔話というのは、一人で字面を追うよりも、大勢で耳で聞くことではるかに力を発揮する。それが、よくよくわかる経験だった。たぶん、映画とテレビの違いもそういうところがあるんだろう。一人でひっそり読みたい本と、大勢で聞きたい本があるように。
と、話がとめどなく流れてしまったが、この本は、山田太一が「考える人」に連載したエッセイが収められている。
阿部知二の「アルト・ハイデルベルヒ」について書かれた章がある。高校の恩師を交えた会の後みんなでタクシーに乗り合わせて帰るのだが、皆で恩師の悪口を言い合う。誰かが降りると、その人の悪口が出る。また降りると、その人を悪しざまに言う。そうやって最後の一人になった男も、心の中で先に降りた男の悪口を言っている。高校時代の友人はやっぱりいいなあ、などと言い合っていたのに、と彼はやりきれない思いで居酒屋の暖簾をくぐる。
山田太一は、学生時代、その本を読み、そういう人間にはなりたくないものだと思ったという。そして、その話を、十二歳年上の兄とたった一回、一緒に飲んだときに話したそうだ。すると、彼は「ほうか。みんな、ほうやって、気張って暮らしとるんだなあ」と言っただけだったそうだ。その後、すぐに兄は亡くなってしまったので、その言葉だけが心に残っている。
中学もろくにでないで就職した兄は、自分のことを言われたように感じたのかもしれない。裏表なしには生きていかれなかったのかもしれない。あるいは、そのくらいの巧言令色はどこにでもあるのに、それが文学となり、世間知らずの学生を感心させるとは子どもっぽい、と思ったのかもしれない。また、むしろ阿部知二は、そういう人間になりたくはないと言いたかったのではなく、人間はもともとそんなもんだ、という訳知り顔を嫌悪してこそこれを書いたのかもしれない。
たった一言の兄の感想から、山田太一はずっと考えてきて、いまも底知れないような気がするという。
本を読み、その感想を言うということは、その人の背景にある様々なことがあるからこそであり、それは、本の内容を超えて、その人の人生を語ることにも通ずる。なんでもない感想の中に、その人のちょっとした経験や、願いや、怒りや悲しみというものがにじみ出ることがある。だからこそ、本を語ることは面白い。
そんなことを、私は考えた。
2015/2/8