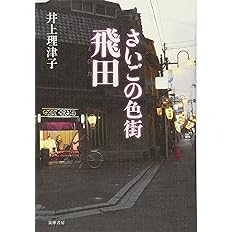20 井上理津子 筑摩書房
2011年発行の本。もう13年前だ。飛田新地は、大阪西成区にある日本最大級の歓楽街。戦後の買春禁止法以降、遊郭は廃止されたが、この本が書かれた当時はまだいわゆる「疑似恋愛」による買春が行われていたという。その後、この場所がどうなったのか、コロナ禍にどう対応していったのかはわからない。たぶん、時代とともに何らかの変化は起きているのだろう。でも、いまだに似たようなことはされていると思う。
「朱より赤く」は芸妓の話だったが、飛田はもっと直截的な遊ぶ場所である。どちらかと言うと「昭和遊女考」に色合いが近い。平成の時代においてもいまだにバンス(前借金)を抱えて顔見世に座り、階段を上がって自室を模した部屋で身体を売る商売が続いていたのだなあ。
この本は、2000年から12年にわたって飛田新地を取材して書かれたノンフィクションである。ここで何が行われているのかを素人の女性が調べるのはなかなか大変だった。飛田新地で遊んだことがある男性に話を聴きたいと言っても、そもそもそんな話をしてくれる人は少ない。また、働いている女性や周辺スタッフ、経営者、周囲を固める暴力団などに取材を頼むのはさらに困難で危険ですらある。そんな中でよく頑張ったものだ。
読んでいて、何ともつらくなって、途中でしばらく読むのを休んでしまった。ここで働く女性も、ここに遊びに来る男性も、ここで稼ぐ人たちも、寂しい悲しい空しい気持ちを抱えている。お金を払って疑似恋愛を買う。キスしてくれたらうれしい、避妊具なしでやらせてくれたらすごくうれしい、また来たくなるという男性は、いったい相手の女性がどんな気持ちでいるのか考えたことがあるんだろうか。避妊具なしの性行為で病気や妊娠などの事態が起きることをどう考えているのだろうか。
目をつぶって棒っ切れ抱いてると思ったら大丈夫、毎日現金が手に入るから、という女性。小さいわが子を家に待たせている人もいる。たいていの女性は家庭に恵まれず、継父や、あろうことか実兄に強姦されて逃げだしてきたような経歴があったりする。彼氏ができても騙される、殴られる、逃げられる。おばちゃんと呼ばれる客との交渉係の女性も、ここでの仕事の満足度は、と問われて「0やね」と答える。経営者にはよくしてもらってる、と言うその口で、だ。経営者も、自分の仕事が世間にばれないように遠くに豪邸を建て、わが子を良い学校に通わせる。飛田新地は撮影厳禁、経営者の名前も一切秘密、古き良き面影を残した楽しい歓楽街という表向きの姿しか公には絶対に見せない。
借金を抱えてここで働きだした女の子たちに、経営者は、例えば成人の日には立派なホテルで食事をさせてやる。良い衣装を着せて写真も撮ってやる。お金が溜まってきたら、ホストクラブを紹介してやる。ちやほやされる楽しみを教え、そこでお金をどんどん使い、借金ができて、また、働く気にもなる。使えば稼ぐしかなくなる。そうやって女の子たちをつなぎとめるという。
後ろめたい、蔑まれる、でも、どんな時代にも必要とされた、絶対になくてはならない場所で、人助けでやっている、と皆がインタビューでこたえる。そうなのか。女性を借金で囲い込んで、毎晩知らない男性に体を売らせる仕事は、いつの時代にも絶対に必要な、無くてはならない仕事なのか。女を金で買う男性がいて、その仕事があるから食べていける女性がいて、その女性をチヤホヤしてお金を搾り取る男性もいる。そうやって毎日みんな頑張って生きて行ければそれでいいのか。
なんとも重苦しい気持ちになってくる。恵まれた環境で育った私(と言っていいのだろう、たぶん)にはわからないことなのか。私は傲慢なのか。肌の温もりの温かさは、お金で買っても、それが見せかけだけの嘘であっても、人を幸せにするものなのか。
権力をもったものが、それをかさに女性を思い通りに扱って、非難される時代がきている。今まではそんなこと当たり前でしょと言われていた、力のある男性が平気で女性を踏みにじる行為。それが批判を浴びる時代がやっときている。そうまでして、自分が偉いと確認したいか。自分が大事にされていると感じたいのか。たとえ大きな力はなくとも、小銭を稼いでそれに近い体験ができるのなら、みんなそれが欲しいのか。
でも、それを非難したり蔑んだりする権利が私にはあるのか。お金も家庭環境も恵まれてきた私がそう感じることにどんな意味があるのか。本当の愛と、ニセモノの愛なんてどう区別できるのか。お金があればそれが幸せなのか。人間ってなんてめんどくさい、なんてへんてこりんな生き物なのか。
ずーんと心が重くなってしまった。身体は、モノだからね。でも、心はモノじゃない。そして、身体と心はつながっている。みんなが幸せになるにはどうしたらいいんだろう。