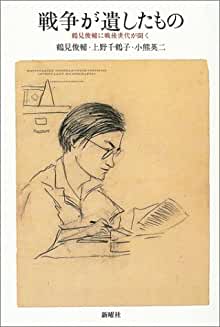59
「戦争が遺したもの 鶴見俊輔に戦後世代が聞く」
鶴見俊輔・上野千鶴子・小熊英二 新曜社
さきごろお亡くなりになった鶴見俊輔さんに、2003年、上野千鶴子と小熊英二が戦中から戦後にかけての経験を聞いた記録である。
もともと小熊氏は、鶴見氏と直接のかかわり合いがなかった。そこで彼は、鶴見氏と面識もあり、フェミニズムの立場から戦後の問い直しに独自のこだわりがある上野氏に共同での聞き取りを持ちかけた。そして、上野氏の快諾を得た後に鶴見氏に手紙を書き、その結果、2003年4月11日から三日間の座談が実現した。先に出版社や編集者の企画を持たない、まさに参加者だけによる記録を、のちに新曜社が引き受けたという経緯である。つまりこれは、彼らの、今、知っておきたいこと、語り残しておくべきものについての極めて純粋なやりとりの結晶である。
深い知識と経験の裏付けのある鶴見俊輔に、思想研究の最先端をいく学者二人が、日本の戦中から戦後の思想史を聞き出すという座談であるから、硬くて小難しくて重たい内容かとおもいきや、これが実に面白く、血沸き肉踊る楽しみと発見にあふれたものであった。こんなにわくわくと本を読み進めたのは久しぶりな気さえする。
鶴見俊輔は、後藤新平の娘の子供で、俊輔という名は伊藤博文からもらったものだという。父は戦後、厚生大臣も務めた大政治家で、いわば日本の中枢を担う名家の血筋である。が、彼は大変な不良であった。座談には何度も「私はヤクザだから」という言葉が登場する。それがまったく違和感がないほどに、彼は万引きや自殺や女性遍歴を繰り返すむちゃくちゃな子ども時代を経て、米国に留学するに至っている。
一高東大を一番で出て大臣になるという「一番病」の父親と、「お前は悪い子だ」と折檻を繰り返す母の間で、「私は悪人だ」という鶴見氏の自己認識が出来上がる。実際、彼は一生自分は悪人であるという自覚の中で生き続けた人だ。だが、その認識は、彼を死ぬまであらゆる権威から自由にさせた。たとえば太宰治のような甘っちょろい自己否定ではない、骨太の、強い意志を伴う悪人意識の凄みをつくづくと感じる。
「思想の科学」の編集、「転向」の共同研究、60年安保闘争やベ平連、従軍慰安婦問題への関わり。一方では「がきデカ」を高く評価するようなサブカルへの深い興味も、彼は併せ持っていた。93歳という長寿の経験談の中には、丸山眞男、竹内好、吉本隆明など著名な知識人から始まって、驚くほど多くのあらゆるジャンルの人物が登場する。そして、その眼差しはどの人に対しても公正で平明である。無名の、小学校しか出ていない、獄死した女性の書き残したものを取り上げて、これこそが真の知識人というものだ、と敬意を持って語る一方で、戦前の行動に口を拭って自分がいかに「民主的」であったかをGHQに申請する知識人たちを冷徹に切り捨てる。言葉の上だけで物事を捉えず、何をしたのか、どう行動したのか、具体的なあり方そのものを見極める。人間一人一人が生きるということそのものが歴史を形作っていくのだということを、身を持って語っている。
そうなのだ。歴史とは大きな枠組を言うのではなく、一人一人の人間が日々をどう過ごしたか、そのことそのものなのである、と私はこの本を読んでつくづくと感じる。ごりっぱそうなことを大きな場所で論じ、世の枠組みを組み替えることだけに意味があるのではない。それだけが歴史を形作るのではない。私は、そのことを以前、この座談の聞き手である小熊英二の「民主と愛国」という本から感じ取ったのを覚えている。そして、鶴見氏は、まさにその「民主と愛国」が素晴らしかった、そのことを根拠に、この本の企画に参加したという。それを知って、私は嬉しかった。
鶴見氏しか知り得ない、様々な思想史上のエピソードがこの本にはあふれている。たくさんある中で、私が感じ入ったのは、彼が金芝河に会いに行った話である。
韓国で金芝河が死刑になりそうな時、小田実に命令されて、鶴見俊輔は彼に会いに韓国へ行く。彼が監禁されている病室に行ったら、何も知らない日本人がいきなり現れたので、驚かれた。
それで私は、英語でこう言った。「ここに、あなたを死刑にするなという趣旨で、世界中から集められた署名があります」とね。金芝河は日本語はできないし、英語もたいしてできない。けれど彼は、片言の英語でこう言ったんだ。「Your movument can not help me.But I will add my name to it to help your movement」(あなたたちの運動は、私を助けることはできないだろう。しかし私は、あなたたちの運動を助けるために、署名に参加する)。
上野氏は「まったく対等の関係から出る言葉ですね。相手に頼るでも、相手を見下すでもない。しかも普遍への意志が感じられる・・・。」と受け取り、鶴見氏も「これはすごい奴だと思ったよ。」と答えている。「もし私だったら、何が言えるだろう。「サンキュー、サンキュー」ぐらいが関の山でしょう。しかも彼は英語がそんなにできないから、ほんとうにベイシックな英語だけで、これを言ったんだ。まったく無駄のない、独立した言葉なんだ。詩人だと思ったよ。」と。
(引用は「戦争が遺したもの」より)
このやりとりのすごさは、言葉を発する者と、それを受け取る者双方の意識の高さによって成り立つものだ。金芝河のすごさを即座に受け取る鶴見氏もまた、素晴らしかったと思わずにはいられない。
2015/8/16